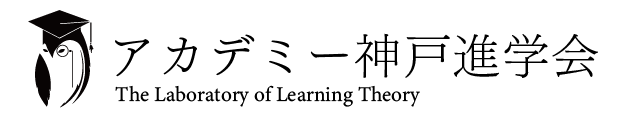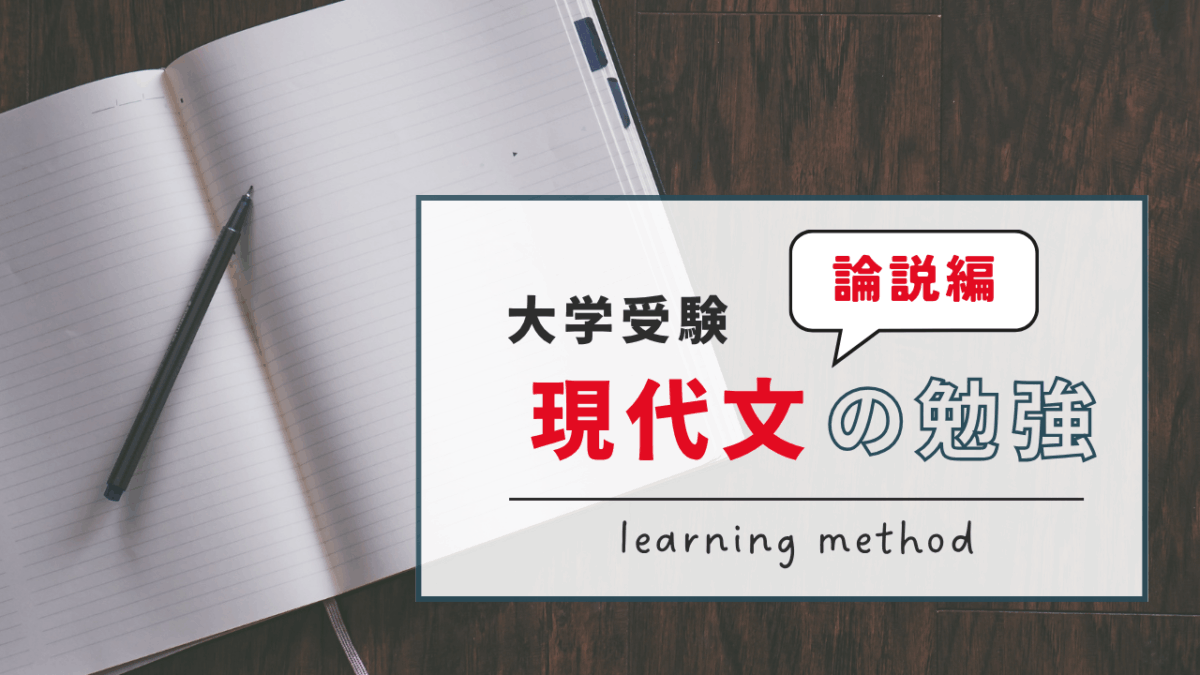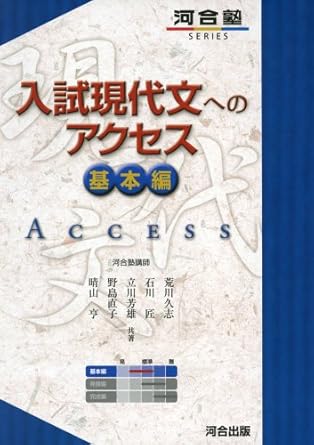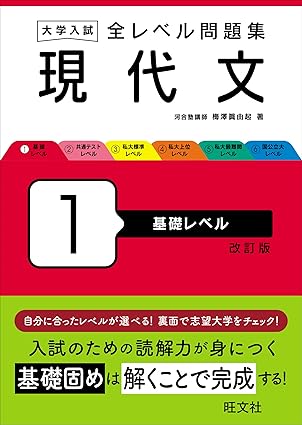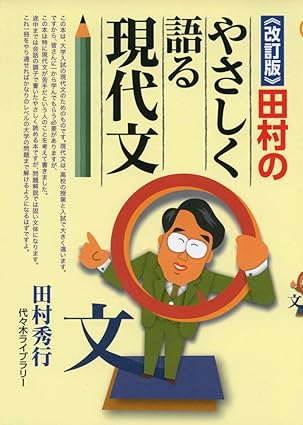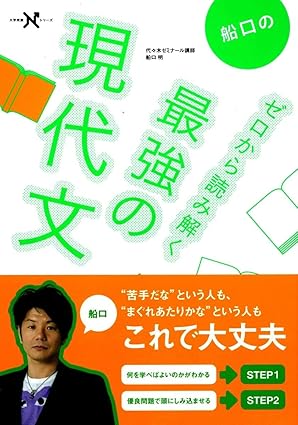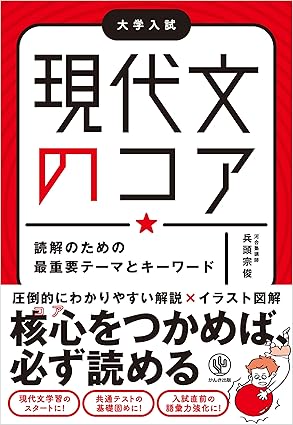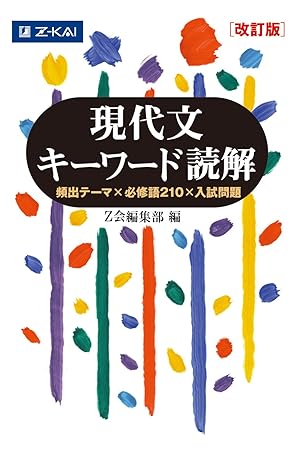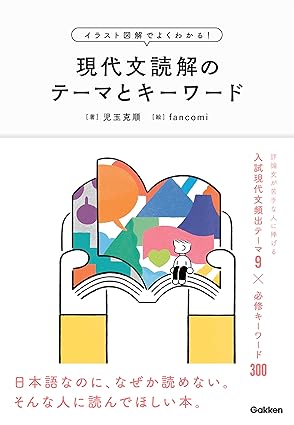現代文って勉強が難しいですよね。
英語や数学と違って、問題集を解いていても
「ここから何を学び取ればいいのか?」
が見えにくい科目です。
だからこそ現代文は
できる人は最初からできるし、できない人はずっとできない科目だと言われることもあります。
そしてこれはある程度は事実です。
現代文は授業や教材を使っての学習よりも、生まれ持っての言語能力や、生活の中で誰とどんな会話をするか、ニュースは見るか、読書はするかなどの習慣による影響の方が大きいと思います。
とはいえ、もちろん勉強によって上達する余地もあります。
というより、生徒たちを見ているとまだまだ持っている力を使い切っていない人が多いです。
今回は現代文の中でも特に論説文に絞り、さらにその中でも
文章の内容を理解する力
に絞って徹底的に解説します。
論説文の
・読み方
・読めない理由
・学び方
・おすすめの参考書
などを書いてますので、参考にして下さい。
対話する
まずは基本のキからいきましょう。
文章を読むときの心構え、姿勢についてです。
文章を読んで「わからない」と言う人の多くは
そもそもわかろうとして読んでいません。
ろくに考えもせずに文章を読み、
早々に設問に進みます。
問題を解くときに傍線部付近だけを注意して読む程度です。
これから読解の技術をいくつか伝えますが、誤解しないで欲しいのは、それらはあくまで“わかりに行く”という姿勢の上に乗って初めて意味があるということ。
例えていえば、難解な文章とはゲームのモンスターのようなもので、技術はそれを倒す武器です。
そして一番大切な「”わかりに行く”いう姿勢」はモンスターに立ち向かう勇気。
いくら武器をたくさん持っていても逃げ回ってばかりでは敵は倒せません。
逆に、武器なんてなくても勇気をもって立ち向かえば素手で倒せるかもしれません。
難解な論説文では技術より前に
「これはどういうことだろう?」
「筆者が言いたいのはこういうことかな?」
と自分の頭で考えることが大前提。
すごく当たり前のことを言ってる感じがしますが、これができていない人はけっこう多いんです。
この「わかりにいく」という感覚は、他科目でもよく生徒に指摘します。
「わからないから教えてください」
というセリフは、一見すると素直で謙虚で向学心のあるスタンスに見えますが、
人によってはこれを
「自分で考えたくないので、わからせて下さい」
という受け身の姿勢で使ってしまっていたりします。
読解でもなんでも、理解の土台になるのは
わかりにいく
という姿勢です。
主張を掴む
例えばあなたが町を歩いていて、突然知らない人に話しかけられたとしましょう。
「ちょっとすいません…」
多分、気になるのは
「この人だれだ?」
ということですよね。もっと言えば
「なんの用だろう?」
ということだと思います。
道を教えてほしいのか、アンケートに答えてほしいのか、試供品を受け取ってほしいのか…
相手の目的がわからなければ、相手の話って入ってきません。
「ちょっとすいません。私この近くにできたスポーツジムの者なんですけど。今10代の方を探してて。ちょっとしたアンケートにご協力いただきたいんですけど。」
普通は「アンケートにご協力」の部分を最重要情報として拾うはずです。
むしろ、この情報までの前段は聞き流している感覚がありませんか?
そして、この情報を拾った瞬間に、なんだか安心感がありませんか?
「なるほど。そのつもりで話を聞けばいいんだな」
と方向性が定まったような感覚があると思います。
つまり、最初に
「結局、なに?」
という問いを発しながら話を聞いているということです。
目的がわかって、ようやく話の中身が理解できるようになります。
読解も同じ。読める人は最初から書かれている内容一つひとつに対して
「はいはい。そうなんですね。なるほどなるほど。」
なんて読み方はしていません。
「とりあえず、おおまかに何の話がしたいのかを、掴もう」
という意識で読んでいます。
「結局、なに?」
ということです。これを論説文では主張を掴むといいます。
(正確には、テーマと主張です)
まず、主張を掴む
これが2番目のポイントです。
現代文のどのテキストにも書かれている基本技術ですが、実際にやろうとすると意外と一筋縄ではいきません。文章にわかりやすく「ここが主張です」と書かれていればよいですが、そんなことはないからです。
ここで必要になる力が
・仮説を立てる力
です。
主張を掴むための
「結局、なに?」
という問いに対して、自分で
「筆者はこういうことが言いたいんじゃないか」
と仮説を立てることです。
冒頭の例でも、話しかけられた瞬間に普通は相手を観察し、仮説を立てるはずです。
「カジュアルな制服を着てるし、どこかのお店かな?だとしたらキャッチかな?」
「スーツを着てるし、お店っぽくはないな。何かのアンケートかな?」
みたいな。
自分で仮説を立てて、それと照らし合わせるように文章を読んでいく方が読解はずっと深く・速くなります。
主張を掴む姿勢=仮説を立てる力
これが2つ目のポイントでした。
具体化する
3つ目のポイントは具体化です。
特に難解な文章を読むときには具体化の力が必要になります。
例えば
「人間は社会的文脈の中で自己同一性を更新する存在である」この文は難しく感じると思います。
実は内容としては当たり前のことを言っているんですが、「社会的文脈」「自己同一性」といった抽象的な言葉を使っているために難しく感じます。
これを
「人は、そのとき置かれている環境や立場に合わせて、自分の考え方や振る舞いを少しずつ変えていく」こんなふうに書き換えるとどうでしょう?
途端に読みやすくなった感じがしませんか?
これは
社会的文脈 ⇒ 置かれている環境や立場
自己同一性を更新 ⇒ 考え方や振る舞いを少しずつ変えていく
このように抽象的な言葉を具体的な言葉で言い換えたため、読みやすくなっています。
文章中では抽象的でわかりにくい言葉は筆者の方で「これだとわかりにくいかな?」と気を利かせて具体的な言葉で言い換えてくれていることもあります。
この筆者が用意した具体化に気づくことも大事な技術なんですが、これは4つ目のポイントで扱うことにします。
ここではあくまで自分で具体化する力にフォーカスしましょう。
どれだけ気の利いた筆者でも、全ての抽象的な内容に対して具体化を用意しておくことは不可能です。
ある程度は自分で具体化することが必要です。
コツとしては、最初から文全体を見るのではなく、言葉のひとつひとつに注目して具体化していくことです。
「社会的文脈ってどういうことだろう?」
「自己同一性ってどういうことだろう?」
とそれぞれ個別に考えて、最後に文全体で意味を統合するようなイメージ。
さらに、めちゃくちゃマニアックな話ですが、
具体化するときの考え方は大きく分けて2つあります。
一つは王道パターン。これは自分が持っている一般知識を使って具体化する方法です。
「フツーに考えてこういうことかな?」
という感覚。
もう一つは経験パターン。これは自分の経験に紐づけて具体化する方法で
「自分の経験の中で探すと、これのことかな?」
というふうに、記憶を探っていくような頭の使い方になります。
例を示すと
「新しい技術は、人々の行動様式に変化をもたらす。」
⇒王道型:スマホによって、誰もが外出先でも情報を検索したり、写真を撮ってすぐにSNSに投稿するようになった。
⇒経験型:最近、紙のメモを使うことがほとんどなくなって、何でもスマホのメモアプリに書くようになった。こんな感じ。細かい話をしているようですが、これらは少し頭の使い方が違うし、どっちが良い悪いは文章や人によって違うので、2つのやり方があることを意識しておくと臨機応変に切り替えられて良いと思います。
具体化に慣れたら、一歩進めて抽象度を意識した読み方をしてみましょう。
選択肢問題にしろ、記述問題にしろ、抽象度が認識できていると答えやすくなります。
イメージとしては抽象度メーターのようなものが自分の中にあって、文を読み進めるたびにそのメーターが上下に動くような感じです。
たいていの文章で、最初は抽象度高く書かれて、それが具体化され、対比等で内容が切り替わるとまた抽象に戻るという感じになります。その抽象度の変化をずっと追跡できるようになるのが大事。
これも例を示してみます。
文1(抽象度高)
現代社会では、人間関係における「距離感」の取り方が、これまで以上に複雑になっている。
文2(抽象度中)
特に、SNSのように誰とでもつながれる環境では、「親しさ」と「礼儀」のバランスを取るのが難しいと感じる人も多い。
文3(抽象度低)
たとえば、友達が自分の投稿に毎回コメントしてくれるのに、自分はその子の投稿をスルーしてしまうと、「無視された」と思われないか不安になる、といった具合だ。
文4(内容が切り替わり、再び抽象度高)
このように、デジタルなつながりが当たり前になる中で、他者との適切な距離を保つための新たなリテラシーが求められている。
抽象から始まり、それがどんどん具体化され、最後に抽象に戻る感じがわかりましたか?
例えば国公立2次試験で出る要約問題などは、めちゃくちゃ乱暴に言えば抽象度の高い部分だけ繋いでいくゲームなので、この抽象度メーターを身につけるだけでもかなり有利になりますよ。
論理構造を学ぶ
4つ目のポイントは論理構造です。
現代文の指導ではよく
「しかし」にチェックを入れましょう
とか
「例えば」をマークしましょう
とか言いますよね。アレのことです。
論理構造とは文と文のつながりです。
当たり前ですが筆者は思いつきで文を並べているわけではなく、何をどの順序で語るかにちゃんと意味を持たせています。
A → B → Cという順番で文を並べたときに、AとBの関係、BとCの関係を見抜くことが論理構造を見抜くということです。
関係の種類はいろんな考え方がありますが、オススメなのは
① 言い換え・具体化
② 対比・逆接
③ 原因・結果
④ 追加・並列
という4種類で考える方法です。
以下に4つの論理構造を詳しく説明したPDFファイルを置いておきます。AIに作ってもらった資料ですが、結構よくできてます。お好きにダウンロードしてください。
(指導者の方もご自由にお使いください)
ただし以下のファイルは簡易版です。ウチの塾生はより詳しく説明した完全版を紙で配布してますので欲しい人は言ってください。
ここからは例を示して説明します。たとえば
近年、若者の読書離れが進んでいる。という文に対しても、4種類の接続が考えられます。
【言い換え・具体化】
たとえば、10代の1日の平均読書時間は、10年前に比べて半分以下になっているという調査もある。「読書離れ」を数値も用いて具体的に言い換えています。
【対比・逆接】
一方で、音声コンテンツや動画での学習はむしろ増加しており、情報との接し方が変化しているとも言える。「読書」とは反対に増加しているコンテンツを挙げています。
【原因・結果】
これは、スマートフォンやSNSなど、活字以外のコンテンツが身近になったことが大きな要因と考えられる。「読書離れ」の原因を述べています。
【追加・並列】
また、手紙を書く習慣や新聞を読む習慣も、かつてに比べて大きく減少している。「読書」と同様に減少傾向にあるコンテンツを列挙しています。
自分が今読んでいる文が、ひとつ手前の文に対して(あるいは筆者の主張に対して)どういう関係性にあるのかに意識を払って読めるようになったら、読解力も設問への解答力もワンランク上がります。
「なんとなく意味は掴めるんだけど、問題に正答できない」
という人には特に有効な方法で、色々な塾・予備校でも指導されています。
知識を得る
最後、5つ目のポイントは知識を得るということです。
これは英語もそうですが、言語というものは言語だけの知識では済みません。
経済の文章なら経済の知識が、
科学の文章なら科学の知識が、
芸術の文章なら芸術の知識があった方が読みやすいにきまってます。
もちろん出題側の配慮として特別にその分野の知識がないと読めないような文章は出題されませんが、それでも出題側が「教養」と捉えるレベルの基礎知識は必要だし、知識はあればあるほど読みやすくなるのは当然です。
文系で、国語が得意な人にありがちなのが
「基本的に現代文はできるが、テーマが”科学”になった途端に正答率がガタ落ちする」
という現象です。
なぜか文系の中でも言語専攻に進みたがっている人は科学やテクノロジーに疎い人が多いんですよね。
いくら言語的な読解力があっても、テーマとして書かれる領域の知識があまりに薄い場合はやはり読めません。
だから、自分が読めない原因がこれまで挙げてきたような読解技術にあるのか、それとも読解とは別のテーマごとの知識・教養にあるのかは分析しておかなければいけません。
それぞれの力の鍛え方
これまでの内容をざっくり整理すると
Point1:「わかりに行く」という能動的な姿勢
Point2:主張を掴む(=仮説を立てる力)
Point3:具体化する
Point4:論理構造を掴む
Point5:知識を得る
こんな感じです。
それでは、それぞれの力をどうやって鍛えていけば良いか見ていきましょう。
Point1:「わかりに行く」という能動的な姿勢
これについてははっきり言ってやる気です。
現代文に限らずすべての勉強に言えることですが、結局自分で考えるしかないという事実を受け入れる覚悟があるかどうかが根底にあります。
あくまでやる気とか覚悟の問題だという前提で、少しでもマシにする工夫があるとすれば
めちゃくちゃ易しい問題集から始める
ということです。
どうしても文章に向き合えない人は、
高校入門レベルや、場合によっては中学レベルの問題集から始めて下さい。
特に頑張らなくても文章はスラスラと読めて、設問にもほぼ満点レベルで答えられるものを選びます。
1冊やり通したら「文章というものは、意味がわかって当たり前」という頭になっています。
この感覚を持ったまま少しずつ文章のレベルを上げていくことで読解の姿勢をつくりやすくなります。
Point2 – Point4:読解技術
Point2~4について、最も簡単な方法は
フツーに問題集を解く
です。
つまり、学習する素材はなんでも良いということ。
学校で配布された問題集
通っている塾の問題集
自分で本屋で買った問題集
なんでもOKです。
ただし、ここで必ずテーマを決めるようにして下さい。
「今回は主張を掴む意識をもって読もう」
「具体化する意識をもって読もう」
「論理構造をに注意を払って読もう」
みたいな感じです。
自分が鍛えるべき力に意識を払うだけで、普段の勉強でも学習効果は全く違ったものになります。
もちろん、自分に合ったレベルや用途の問題集を使うと学習効果は上がります。
この記事の最後にもオススメの問題集を挙げていますので、気になる人はそちらを参照してください。
また、ウチではそれぞれの技術を集中的にトレーニングするためのオリジナル教材をつくっています。
【仮説形成問題-例題】
朝の駅前には、スーツ姿の大人たちの列ができる。足元を見れば、革靴の色が交互に並び、歩幅が揃っているようにも見える。傘の先が互いに触れそうなほど、一定の距離感を保ちつつ、列はすっと伸びていく。
先日、ひとりの若い男性が、その列の間に割って入った。誰かが舌打ちしたが、声を上げる人はいなかった。そのまま数秒が経ち、列は少しだけよじれた。やがて電車が来て、列はそのまま車内へと吸い込まれていった。
残った空間には、誰のものともつかない不協和音のようなものが揺れていた。それは怒りというより、空気の乱れに近い。
【問題】
上の文章からテーマを自由に想像してみてましょう。こちらが主張を掴むトレーニングの例題。
試作期のものなので文体が少し物語調ではありますが、一見するとただ説明をしているだけの文から
「この話題を通して何を主張したいんだろう?」
「この後はどのように論が展開されるんだろう?」
という仮説を立てるトレーニングです。
うちのトレーニングはコーチングの考え方に基づいて設計しています。
コーチングの本質は「意識の焦点」
これまで漫然と読んでいた生徒が、どこに意識を向け、どういう頭の動かし方をすればいいのかを体験的に掴むことができるようにつくっています。
他の2種類も紹介しておきます。
<課題文>
経済とは、交換の制度化である。
個人の欲望や判断は、そのままでは混沌を生むが、貨幣や市場の仕組みがそれを秩序として組み上げていく。
経済は、無数の利害を調整するための構造なのだ。
________________________________________
<具体化のための思考ガイド>
1.「交換の制度化」とは、どんな仕組みのこと?
2.「混沌→秩序」への変化は、どう生まれている?
3.「利害を調整する構造」としての経済の例は?
________________________________________
<具体化の例>
① 王道型(制度としての経済)
経済とは、たとえば「お金を払ってパンを買う」ような、モノやサービスの交換がルール化された仕組み。人の欲望は本来バラバラだけど、貨幣という共通の尺度があることで、価格が決まり、売り手と買い手が合意できる。つまり経済とは、交換をスムーズにする制度なのだ。
② 経験型(日常での実感)
学園祭の模擬店で、人気のメニューは早く売り切れるし、そうでないものは値引きされる。お金を介して「何が求められているか」がはっきりし、売り手と買い手の行動が変わっていく。こうした小さなやり取りにも、経済という“構造”が見えてくる。
こちらは具体化のトレーニング。
課題文はあえて抽象的な言葉を多用してあります。
一つひとつの言葉に注目して、自分なりに具体化を重ねていくことで文全体の意味を解釈しようというトレーニング。
勉強しやすいように思考のガイドとしていくつかの問いをつけています。
さらに解答としての具体化例には王道型と経験型の2パターンをつけているので幅も広がります。
このトレーニングを通してわかりにくい言葉は自分で具体化する意識を習慣化していきます。
【論理構造トレーニングー例題】
資本主義は、個人の利益追求が全体の利益につながるという構造を持っている「市場の見えざる手」によって社会が調整されるという考え方である。たとえば、自分のためにパンを焼くパン屋が、結果的に地域の人々の生活を支えるように、市場は秩序を生み出すとされてきた。
確かに、資本主義は経済成長や技術革新を促し、豊かさを実現してきた。しかし一方で、格差の拡大や環境破壊など、深刻な副作用も顕在化している。こうした問題は、単なる制度設計のミスではなく、資本主義の構造そのものに起因する可能性がある利潤を最大化しようとする企業の行動が、労働の不安定化や資源の浪費につながっているのだ。
このような背景から、近年では「経済の目的とは何か」を問い直す動きが広がっている。たとえば、幸福度や持続可能性を基準にした経済政策の提案や、共同体重視の社会主義的価値観の再評価などが挙げられる。
■ 設問
上の文章を読んで、論理展開を図解せよ。以下の記号を用いて、構造を視覚化してみよう。
「=」:同値・具体化などのイコール関係
「↔」:対比や逆接関係
「⇄」:因果関係
「↳」:追加・並列関係これは論理構造を掴むトレーニング。
文章から4つの論理構造を見つけだして自分なりに図解してもらいます。
文章はかなりリアルに寄せていて、短めの文章ですが4つの論理構造がすべて含まれるように設計されています。
多くの指導者が取り入れているように、文章に印を入れる方法も良いんですが、オススメなのはこの問題のように図解してしまう方法です。
印を入れるだけだと意味をあまり考えずともできてしまいますが、図解はちゃんと考えないとできません。
手を抜くことができず、半強制的に鍛えたい力を鍛えることができます。
ちなみに、これらの3種類のトレーニングは
経済、テクノロジー、政治、芸術、自然科学、歴史・近代、言語・コミュニケーション、倫理・哲学・宗教、社会・文化
という厳選した9つのジャンルから各5テーマ、合計45テーマを通して知識を得るという効果も期待できるようにつくっています。
けっこう良いものができたので、こちらは一般の指導者の方でも使えるようにnoteの有料記事として購入できるようにしていきます。
ウチの塾生は当たり前ですが無料ですので、普段の学習に取り入れたい人はリクエストしてください。
あと、たまに試作問題のテストとして僕から一方的に押し付けられるかもしれません。
知識を得る
現代文に必要な背景知識は、実は勉強するのが最も難しい領域です。
なぜなら、基本的にこれは日常生活の中で獲得する割合が大きいからです。
勉強というよりも、日常の習慣の差がモノを言います。
例えば読書をする習慣がある人、ニュースやドキュメンタリーを見る習慣がある人は背景知識を得やすくなります。
最大の効果を求めるなら日常の習慣を見直すところから始めて下さい。
ただ、もちろん勉強も大切です。
勉強の中で知識を増やすなら、意味の分からない言葉を調べる習慣を持ちましょう。
一つひとつ調べて、理解する。そうやってコツコツ増やすしかありません。
勉強の時の注意点として、意味の丸暗記はやめて下さい。
辞書を引いたり、現代文用語集のようなものを使うと確かに言葉の意味が端的に説明されています。
しかし、その説明文を見ること、あるいは説明文を暗記することは言葉を増やすことには繋がりません。
言葉というのは理解して初めて効果があります。
そのために基準にして欲しいのは
言葉→意味→例文→文脈
という順番です。
言葉を知らないなら意味を調べる。
意味を見てわからなければ例文を調べる。
例文を見てわからなければ文脈の中で出会う。
例を示してみます。
① 言葉
パラダイムシフト
② 意味
それまで当然とされてきた考え方や枠組みが根本的に転換すること。
③ 例文
「インターネットの普及は、情報の扱い方に大きなパラダイムシフトをもたらした。」
④ 文脈
「産業革命以降、蒸気機関や電力、コンピュータなどの技術革新は人々の生活様式や経済の仕組みを大きく塗り替えてきた。近年ではAIや再生可能エネルギーの発展が新しい価値観や制度を生み出し、これまで当たり前とされてきた働き方や社会の在り方そのものにパラダイムシフトを引き起こしていると指摘される。」どうですか?
辞書的な意味を見ただけではわかりにくかったのが、例文を見るとなんとなくわかり、文脈の中で出会うとさらに意味の輪郭がはっきりした感じがしませんか?
このように周辺情報を多くするほどに言葉は理解しやすくなります。
理解できると達成感があるので次へのモチベーションにもなります。
知識をつけるなら、必ず理解を伴うように。
そのために言葉→意味→例文→文脈という順序を意識してみて下さい。
おすすめの参考書
さて、いつも通り超大作な記事になっていますが、最後にオススメの参考書を紹介します。
まずは読解の問題集から。
読解の問題集を選ぶポイントは、本文解説がついていることです。
例えば模試や過去問の解説は、基本的に設問の解説しかついていません。
解説が始まるといきなり
問1
(ア)筆者は本文中でーーーと述べており、不適。みたいな解説が載っています。
これだと設問の解き方に意識がフォーカスしてしまい、肝心の本文をどう読み、どう捉えたかに意識が向きません。
だから最初のうちは本文読解がしっかり載っている参考書を使うのがオススメ。
この2種類のシリーズはその意味でオススメ。
とりあえずこの辺使ってれば間違いないという感じ。
もちろんこれは模試や過去問を否定しているわけではありません。
読解力のある人が、志望校に合わせて設問の分析や答え方の調整をする作業は必要です。
あくまで自分の状況や鍛えたい力に合わせて決めましょう。
現代文がめちゃくちゃ苦手な人はこのあたりから。
背景知識を得たいならこのあたり。
迷ったら『キーワード読解』でOK。
図解多めなら『テーマとキーワード』です。
まとめ
いかがでしたか?
読解の中にもいろいろな頭の使い方があることがわかってもらえたと思います。
最後にもう一度ポイントを列挙しておきましょう
Point1:「わかりに行く」という能動的な姿勢
Point2:主張を掴む(=仮説を立てる力)
Point3:具体化する
Point4:論理構造を掴む
Point5:知識を得る
これらを身につけて「読む力」さえつけてしまえば、現代文は基本的になんとなります。
選択問題だろうと、記述問題だろうと、要約だろうと、本質的には
「読めた?」
と聞いているわけですから。
そして何より「文章が読める」というのは一生モノの能力です。
多分受験勉強で培われる力の中でトップクラスに一生使います。
色んな本が読めると楽しいですよ。
頑張って本物の読解力を身につけて下さい。