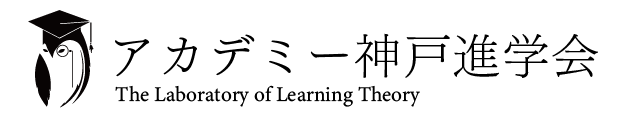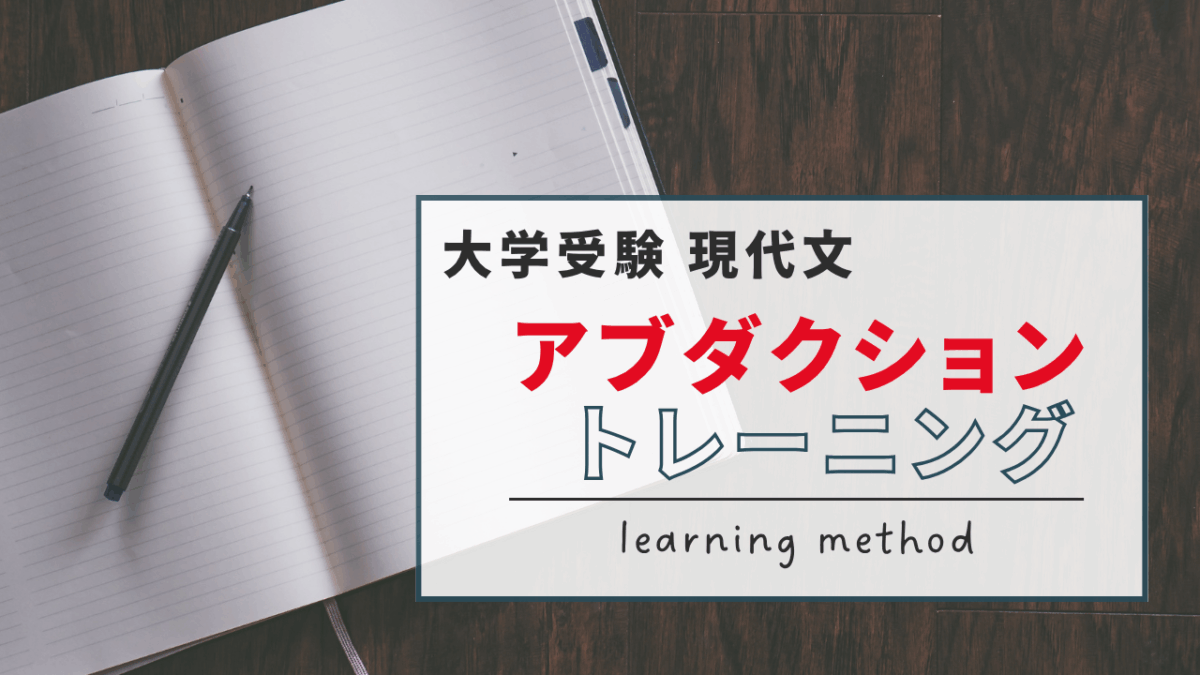現代文のトレーニングを開発中
去年の11月ぐらいから現代文について再研究しています。
生身の人間が教える塾だからこそ、学習法の専門塾だからこそできるトレーニングを開発するのが僕の基本コンセプトなんですが、今回なかなか良いヤツがつくれたのでご紹介したいと思います。
現代文のトレーニングで、特に論説文に有効。
文章はAIに作らせているんですが、問題のつくり自体が新しく、オリジナルなものが作れたんじゃないかと思っています!
ちなみに大人の方がやっても楽しめると思うので、社会人や保護者の方もよければチャレンジしてみて下さい。
読める人がやっていること
読める人は読解の中で色んなことを考えています。
(理解力も記憶力も、その原点は思考力だと僕はいつも伝えています)
その中の一つが「仮説と予測」です。
読解ではよく「筆者の主張を読み取ろう」と言われます。
確かにそうなのですが、より正確に言うなら、読める人がやっているのは「読み取る」ではなく「仮説を立てて、それと照合する」という思考です。
まだテーマや主張が提示される前から
「この文章のテーマはこういうことじゃないか?」
「筆者はこういうことが主張したくて書いてるんじゃないか?」
という自分なりの仮説を立てて
「だとすると、この文章はここからこんなふうに展開していくはずだ」
という予測を立てます。
この仮説と予測が読解力を支えています。
この仮説は当たってなくても構いません。
もし仮説通りならスラスラ理解できてラッキーだし、仮説が外れていれば
「あれ?おかしい」
と違和感を覚え、読みを修正すればいいだけです。
この仮説を立てる力はアブダクションとも呼ばれ、知能や学力を支える重要なファクターであることがわかっています。
実際に受験指導をしていても、このアブダクションの力が高い人は現代文に限らずどの科目においても理解力が高く、点数も伸びやすいです。
今回紹介するのはこのアブダクションの力を鍛えるトレーニングです。
やってみよう
トレーニング内容はシンプルです。
今から短めの文章を提示します。
これは、論説文を読む時の出だしの文章だと思って下さい。
このような文章から論説文がスタートしたら、そのテーマは何で、ここから論がどう展開していくのかを予想してみるというトレーニング。
感覚を掴むためにまずは例題と解答例を出します。一度見てみて下さい。
夕方、スーパーのレジで会計をしていたときのこと。
前に並んでいた高齢の女性が、財布の中を何度も確認しながら硬貨を出していた。
数枚の小銭を手のひらでひとまとめにしようとするが、いくつかがこぼれて床を転がった。
レジの音も、周りの話し声も一時的に消えた気がした。
その人はそれらをすぐに拾い、会釈しながら静かに会計を終えた。
袋詰めの台までの歩き方も、やけに丁寧だった。
少し物語調の文章です。試作段階でAIが上手く調整できていない時のヤツなんですが、例題にする分には問題ないので出題してみました。
この文章を、あくまで論説文の出だしだと想定して、テーマを考えてみましょう。
解答例は以下
「時代の変遷と、それに伴う豊かさの変化」
今はキャッシュレスも進み、レジでのやり取りはスムーズであることが前提で、この高齢女性のような行為は煙たがられます。でも、女性の動作の端々から上品さも感じます。時代が時代なら微笑ましい光景が、現代ではそうではない。この女性に時代に取り残された悲壮感のようなものを感じました。
これは僕の解答例ですが、この問題に正解はありません。
あくまで
「このエピソードは何を主張するために選ばれたんだろう?」
と頭を働かせること。
この意識のクセをつくることが、このトレーニングの目的です。
AIに文章をつくらせているのがポイント。
本から引用しようとすると、適切なレベルのものを探すのに膨大な時間がかかります。
また、AIが書くことで僕が「解答者」の立場でいられるのも大きい。
生徒と同じ立場でお手本を見せたり、思考プロセスを伝えることができます。
すごく画期的ですよね(笑)
では、次の問題は少しだけ時間を取って考えて見て下さい。
朝の駅前には、スーツ姿の大人たちの列ができる。足元を見れば、革靴の色が交互に並び、歩幅が揃っているようにも見える。傘の先が互いに触れそうなほど、一定の距離感を保ちつつ、列はすっと伸びていく。
先日、ひとりの若い男性が、その列の間に割って入った。誰かが舌打ちしたが、声を上げる人はいなかった。そのまま数秒が経ち、列は少しだけよじれた。やがて電車が来て、列はそのまま車内へと吸い込まれていった。
残った空間には、誰のものともつかない不協和音のようなものが揺れていた。それは怒りというより、空気の乱れに近い。
これはAIを調整して少しだけエッセイ調に寄せました。
さて、この文章のテーマは何で、ここからどう展開していくと思いますか?
「秩序と空気」
秩序をつくるのは規則ではなく、人々が作り出す空気だったりします。 認知的不協和という言葉もありますが、みんなやっているのに自分だけそれをしない(あるいは、逆)はストレスになります。 日本人は特に右に倣え的な性質が強いので、その秩序の度合いも強くなりそうです。 だから日本は安全で、規律正しく、逆に言えば異質なものに不寛容だ、と展開していく。
これが僕の解答例です。
いかがですか?
ちなみに、生徒たちにやってもらうと
「同調圧力についての話」
という意見が多かったです。
僕の解答と近いですが、僕は功罪をフラットに見ているのに対して、生徒たちは「同調圧力=ネガティブなもの」という面のみに意識を向けていました。
これ、面白いですよね。
文は若者の迷惑行為に見えますが、生徒たちはむしろその行為には寛容で、一律を強要する社会の方に嫌悪感を抱いているようでした。普段から抑圧される環境にある生徒たちは大人以上に同調圧力に敏感に反応するのかも。
重ねて言いますが正解はありません。
むしろ、このような解釈と予測の違いを話し合ってみるのも良い学びになるでしょう。
家族や友達とやってみるのも良いですね。
授業でやるならもちろん僕と意見交換することになります。
これがウチのような個別指導形式の中でこのトレーニングをやる醍醐味かなと思います。
もっとやってみよう
さて、感覚は掴めましたか?
まだ試作中なので文体が安定しないのは申し訳ないですが、いくつか問題を出してみます。
祖父の書斎には、使い古された万年筆が一本だけ置いてある。
もう何年も前にインクは乾き、今ではただの静かな物体だ。
けれど祖母は、毎月の命日にその万年筆を丁寧に拭き、位置を少しだけ整える。
いつも、棚の端からほんの指一本分だけ真ん中に近づくように。
そこに意味があるのかはわからない。
でも、その動作が誰かの時間を支えているように思えた。
これは少し物語調ですが、いかがでしたか?
「故人への想い、または人の死とは」
祖父の生前にも祖母は書斎を掃除して、その時に万年筆をその位置に置いていたのかもしれません。大事な万年筆を落としてしまっては大変だから、端に置くなと言い含められたのかもしれません。モノや動作を通して、生前の故人と繋がる。またはそれらの動作が故人の「存在」を代替する。 これがエッセイ調の論説文なら、このような些細な動作や、もう少しスケールの大きな「儀式」などを通して故人の「存在」とどう折り合いをつけてきたのかを語る文章が予想できそうです。
僕の解釈はこんな感じ。
ここまで言語化できてなくてもいいですよ。
美術館で見た絵に、なぜか強く惹かれた。
風景画だった。緑が多く、曇り空の下に広がる静かな丘。特別な技法があるわけでも、派手な色づかいでもなかったけれど、その場から離れがたくて、しばらく立ち尽くしていた。
後ろから来た人に押されるようにしてようやく次の作品に進んだが、その後も頭の片隅にずっとその絵が残っていた。
帰り道、ふと思い出した。あの風景、昔よく家族で出かけた公園の丘に似ていた。
きっとあの絵に惹かれたのは、「絵の中に自分の記憶を見たから」だったのかもしれない。
今回はジャンルを先に提示してみました。
ジャンルが先にわかっていると少し解釈が方向づけされる感じがしますね。
ちなみにこれはAIの調整が上手くいって論説文の書き出しとしてもありそうな文体が実現しました。
「芸術が伝えるもの」
芸術は表現者の中にあるものを鑑賞者に伝えるだけではなく、むしろ鑑賞者の中にあるものを作品を通して喚起したり、再発見したりすることにある。 想像力を持って作品と向き合うことの重要性を説く論理展開も予想できますね。
ジャンルが指定されているとストレートな解釈になりました。
これも発見。
昼過ぎのパン屋は、店主と常連のやりとりで少しにぎやかになる。
手書きのレシートに、釣り銭を探してあたふたする手。
小銭入れの奥に指を突っ込み、1円玉をかき集める常連客を、
後ろに並んでいた男が苦笑しながら手伝った。
会計が終わると、店主はいつもより少しだけ深く頭を下げた。
レジの横の端末には、「セルフレジ準備中」の文字が貼られている。
今回もジャンル提示問題。
手書きのレシートはさすがに非現実ですが、テーマを損ねるほどではないので放置しました。
「経済活動の合理化で失われるもの」
手書きのレシートに手動の会計は現代では非合理ですが、そこには人と人のやり取りという経済活動の本質があるとも取れます。 セルフレジ準備中なので、合理化することによって今後は人と人が直接関わることがなくなることが示唆されていますね。そのことへの物寂さからか、店主はあと僅かとなったお客とのやり取りを噛み締めるように深く頭を下げます。経済活動の合理化が本当に人間を豊かにしているのかを問うような展開が予想されますね。
僕の解釈はこれ。こちらもストレートだと思います。
線路の向こうに、小さな倉庫のような建物がある。
窓もなく、扉は少しだけ開いている。
中の様子はわからない。
朝と夕方、決まった時間に誰かが出入りしているようだ。
顔は見えないし、会話もない。
でも、地面の踏み跡が少しずつ変わっている。
何をしているのかはわからない。
ただ、そこに何かが続いている気配だけがある。
これはAIとのやり取りで生まれた激ムズ問題。情報量を限りなく減らしています。
抽象的な文章だけに自由な解釈・仮説が成り立ちます。
「自己の相対化、あるいは、人生の交差」
目的不明の倉庫、ルーティン的な人の出入り、正体はわからないが「何か」が持続していることだけがわかる。 これは「自己からみた他者」あるいは「他者から見た自己」と言える気がします。 ある人から見える他の人は、ほんの足跡程度の情報でしかない。人は自分の物語しか認識・蓄積できません。でもそれは他の人から見た自分も同じ。ここをもって自己の相対化。 でも文章では倉庫と足跡の存在に気づき、何かを感じ取った人がいます。ほんのわずかでも人生が交差した瞬間にも思えます。
僕の解釈はこれ。かなり飛躍のある解釈ですが、これだけ文が抽象的だと仕方ないかなと。
ここまでいくと文章自体は受験からかなり離れてしまってますが、使っている力は同じであることを考えれば、こういうのもアリかなと思っています。
こんな感じのトレーニングです。
いかがでしたか?
ちょっと頭の体操になったのではないでしょうか?
最後にこのトレーニングで鍛えられる力と、意識すべきポイントを整理しておきます。
鍛えられる力
1.仮説を立てる力(アブダクション)
もちろんメインはアブダクション。
「わからないとか言う前に自分なりの仮説を立てなさい」
と僕に言われたことがある生徒も多いと思いますが、学力をつける上でめちゃくちゃ重要です。
そもそもアブダクションをするという発想がない生徒も多いので、そういう生徒にスイッチを入れるというのも大事な目的です。
繰り返しになりますが正解はないので、自由に発想して下さい。
自分なりの仮説を立てること自体が、このトレーニングの目的です。
誰かと一緒にやるのも有効です。
ゲーム感覚で誰かと共有すればより刺激も得られるし、自分にはなかった解釈を発見するチャンスです。
家族や友達とチャレンジしてみましょう!
授業では僕の解釈も伝えるし、立ててくれた仮説に対してのフィードバックも行うので、より効果が高いと思います!
2.抽象化する力
仮説を立てる上で大事になるのが抽象化です。
提示される文章は全て具体的なエピソードです。
パン屋→商売
絵画→芸術
万年筆→形見
こんなふうに各要素を抽象化して捉えることで仮説を立てやすくなります。
3.言語化する力
実際に体験してくれた生徒が揃って口にするのが
「感覚的にはわかるけど、言語化が難しい」
という感想。
現代文では選択式か書き抜きの問題が多いですが、それはいわば「誰かの言葉を借りている状態」です。
でも今回は抽象化して仮説を立てるので言葉を拝借できません。これによって言語化の力もセットで鍛えられます。
読解の力と言語化の力は繋がっているので、読解の力もより高まるし、もっと直接的に記述問題や作文・小論文の力に繋げることもできるでしょう。
このトレーニングはまだまだ可能性を秘めていて、もう少しアレンジのアイデアもあるので研究予定。
夏休みには間に合わせますので、現代文の力を強化したい人は一緒に取り組みましょう!